冬至といえばかぼちゃと柚子湯、その由来は?

一般的には風邪をひかないためや
語呂合わせと言われていますが…ちゃんとした理由があります!!
冬至とは
※12/21頃。毎年変動
北半球において太陽の位置が1年で最も低くなる日で、日照時間が最も短くなる日。
一陽来復
1年で最も日が短いということは、翌日から日が長くなっていくということ。
そこで、冬至を太陽が生まれ変わる日ととらえ、古くから世界各地で冬至の祝祭が盛大に行われていました。
何故かぼちゃ?
冬至には【ん】のつくものを食べると【運】を呼び込めると言われています。
にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん……など
「ん」のつくものを運盛り といい、縁起をかついでいたのです。
何故かぼちゃかと言うと漢字で書くと【南瓜】なんきんになるからなんです。
さらに、陰から陽へ向かうことも縁起がよいとされています。
何故ゆず湯?
柚子(ゆず)=「融通」がきく、冬至=「湯治」。
こうした語呂合せから柚子湯に入ると思われていますが、
もともとは運を呼びこむ前に厄払いするための禊(みそぎ)だと考えられています。
「邪気を払ってくれる」
「1年じゅう風邪をひかない」
と言われ、日本では江戸時代から広く伝わる習慣となっています。


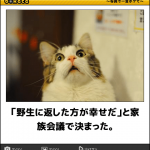





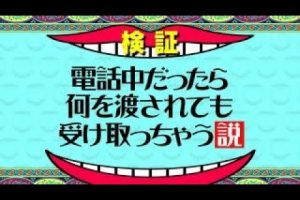







コメントを残す